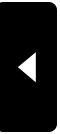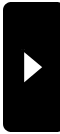2011年08月02日
明善寺だよりNo.3
何をしている風景でしょうか?

答え.明善寺本堂の正面から見た左側面の屋根の葺き替えです。

合掌造りは、大規模な屋根の葺き替えは30-40年に1度行なわれます。
かつては、村人総出で相互の補助の助け合い『結』の精神で行なわれていました。

現代社会の私達に受け継いでいきたい精神の1つだと思いました。
白川郷 平瀬

答え.明善寺本堂の正面から見た左側面の屋根の葺き替えです。
合掌造りは、大規模な屋根の葺き替えは30-40年に1度行なわれます。
かつては、村人総出で相互の補助の助け合い『結』の精神で行なわれていました。

現代社会の私達に受け継いでいきたい精神の1つだと思いました。
白川郷 平瀬
Posted by
文教スタヂオ
at
20:22
│Comments(2)
│今日の出来事
この記事へのコメント
私の実家は今も残っていますが、古い茅葺の農家です。今は屋根をトタンでかぶせており屋根のふき替えはしませんが、私が小さいころは近所の人が総出で葺き替えをしていました。昔は家の中で薪をくべてお湯を沸かしたり、お釜でご飯を炊いたり、お風呂をわかしており、家の中はもちろん屋根にまで煙が行きわたり、防虫・防腐効果をもたらしていました。同時にススが家中に充満して付着し、強い風が吹けば家が“ミシッ”と音を立て、ススの塊が落ちてきます。夏と年末に家中の畳を上げ、長い竹の先にササを付け、天井についたススを払うのが年中行事でした。
ですから、屋根の葺き替えの時は皆顔をススで真っ黒にされていたのを覚えています。現在の白川郷では葺き替えの人の顔は黒くないので、現代だな~、と思います。
ですから、屋根の葺き替えの時は皆顔をススで真っ黒にされていたのを覚えています。現在の白川郷では葺き替えの人の顔は黒くないので、現代だな~、と思います。
Posted bysawatoat2011年08月03日 11:35
昔は、屋根に迄、すすが行きわたる程だったのですねー。
茅葺きでなくても、毎日の積み重なった生活のすす(ホコリ)等、
掃除は、大変ですが、それ以上の苦労が昔にはあったんデスネ!!
茅葺きでなくても、毎日の積み重なった生活のすす(ホコリ)等、
掃除は、大変ですが、それ以上の苦労が昔にはあったんデスネ!!
Posted by白川郷 平瀬at2011年08月04日 17:00